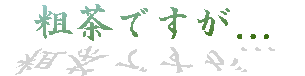嘘から出たマコト
残り時間はあと一週間。
しかし、シンには何も浮かばなかった。
それは一週間前の学級会でのこと。先生が黒板に書いたのは「自分」という二文字だった。
そして、先生は言った。
「 来週と再来週の学級会で「自分」だと感じるものを発表してください。
どんな発表の仕方でもかまいません」
シンには先生の言っている意味がさっぱりわからなかった。
ほとんどのクラスメイトも悩んでいるようであったので、シンは少し安心した。
しかし、今日の発表を見ておどろいた。
みんなさまざまなやり方で「自分」を表現しているようだった。
幸い、シンは名簿の順番が遅かったのであと一週間はあるが、考えてもどうしてもわからなかった。
表現方法はさまざまだが、大抵の生徒は「魔法」を使っていた。
「魔法」とは思春期になった子どもがある日突如として身につくものである。
現れ方はさまざまで個人差がある。また、全くその症状が現れない子どももなくはない。
そして、大人になると自然と消えてしまうのが通例だが、
なかには成人しても魔法が使える人も少なくなかった。
その「魔法」はまだシンには現れていなかった。
シンは焦っていた。
発表するものが決まらないことと、みんなが魔法を使えることに対して。
そんなときだった。放課後になり、シンが帰り支度をしていると、
前の席の女の子にクラスメイトが集まっていた。
先ほどの学級会での発表で、空を飛ぶ魔法を使ったのだ。
彼らの会話は次第に魔法の話になり、それぞれの魔法を教えあっていた。
すると、突然一人の生徒がシンに話を振ってきた。
「シンくんはどんな魔法持っているの?」
シンが言葉を濁していると、一人の女子が、
「背高いし、すごいの使えそうだよね」
と、勝手な想像を口にした。すると、みんなもうなずいていた。
こういうとき、シンの口は自動的に動くのだった。
「うん。おれのはね、すごいよ。だって人が出せるんだよ」
「えっ、人?」
「しかも、おれと同じ顔の、おれそっくりな人間なんだ。
触れないんだけど、ちゃんとしゃべるんだよ」
「すごいねえ。見せて、見せて」
「でも、この魔法使うとすっごく疲れちゃうんだよ。
もう、くたくたになるんだ。でも、もしかしたら学級会のとき見せられるかもしれない」
「えー今見たい」
「お前、無茶いうなよ」
「絶対、見せてね」
こうしてシンはその場をしのいでいた。
家に帰ると、シンは自分の部屋で寝転んでいた。
みんなにあんな嘘をついてしまったことを後悔していた。
「おれも魔法が使えたらなあ」
このまま魔法が使えないのかと思うと、シンはとても怖くなった。
クラスのみんなが使えるのに一人だけ使えないのは嫌だった。
もしかしたら馬鹿にされるかもしれない。そのうえ、シンは母親のことが気がかりだった。
数日前のこと、シンが魔法を使えないことを母親は父親に相談しているところを見てしまったのだ。
シンは何とかして魔法が使えるようにしようと思った。
とりあえず、体を鍛えてみようと思い腹筋を二十回やったが、効果は出なかった。
次に、庭に出てなわとびを五十回してみたが、やはり効果はなかった。
途方に暮れたシンは縁側に腰を下ろして庭を眺めていた。
桜の木はすっかり葉桜となっていた。
それを見つめていると急に睡魔が彼を襲い、シンは倒れこむように眠ってしまった。
数分後、シンは目を覚ました。
庭から子どもの笑い声が聞こえたからだ。
「そんなところで寝ているとかぜ引いちゃうよ」
そのぼんやりとした子どもが言った。
眠い目をこすってその子を見た。その顔は毎日鏡越しでしか見ない顔。
つまりシンにそっくりな顔をしていた。シンはおどろいて声も出なかった。
「あはは、びっくりしてる。でも、シンが望んだことじゃないか」
「じゃあ、お前は……」
「ぼくはマコト。君の魔法だよ」
マコトはにっこりと微笑んだ。
シンの魔法だからだろうか、マコトとシンは好みがまったく一緒で、すぐに仲良くなった。
シンは早くこのことを母親に伝えたかったが、あいにく今日の帰りは遅かった。
結局、シンは眠ってしまい、マコトを見せることは出来なかった。
その次の朝、すぐさま教えようとしたがシンが呼んでもマコトは出てこなかった。
しかし、学校での休み時間の時、突然マコトが現れた。
「うわ! 急に出てくるなよ!」
「へへ、だって退屈なんだもーん」
と、マコトははしゃぐように笑っていた。
「学級会までみんなに内緒にしなきゃいけないんだからな!」
「ふふふ、大丈夫だよ」
「いいから、はやく消えろ」
と、そのとき、ふいに後ろから声が聞こえた。 「シンくん?」
急いで振り向くと同じクラスの女の子だった。
「あ……、これは、いや……」
「でっかいひとりごとだね。誰かとしゃべっているのかと思った」
「え?」
振り返るとすでにマコトはいなかった。
家に帰ると母親がいた。さっそくマコトのことを話した。 そして、マコトを見せようとしたが、マコトは現れなかった。
しかし、自分の部屋に入った途端、マコトが現れた。
「お前、何やってたんだよ」
「だってみんなに内緒にしなきゃいけないっていってたから」
「母さんはいいんだよ! さあ、見せに行くぞ」
「嫌だ! 誰にも会わない!」
「なんだと! おれの魔法のくせに口ごたえすんじゃねえ!」
と、二人はとっくみあいの喧嘩を始めてしまった。
すると、部屋をノックする音が聞こえた。心配そうな顔をした母親がそこにいた。
「どうしたの。ひとりで大きな声を上げて」
振り返ると、やはりマコトは姿を消してしまっていた。
「……ごめんなさい」
「魔法のことは気にしなくていいのよ。みんなそれぞれ違うんだから」
「はい……。あの……母さん、その……」
「何?」
「ぼく以外の声、聞こえなかった?」
「いいえ、シンの声しか聞こえなかったわ」
そういって、母親は部屋を出て行った。
それからも、マコトは勝手気ままに現れては消えた。
その回数は日を追うごとに頻繁になっていった。
しかし、けして人に目撃されることはなかった。
シンはこの魔法が使えるようになって安心していたが、扱えていないことに不安を感じていた。
学級会はもう明日に迫っている。うまく発表できるか、心配だった。
今日もまた突然マコトは出てきた。しかも授業中だった。
「おい、はやく隠れろよ」
シンは小声でマコトに言った。
「嫌だよーだ」
相変わらず、マコトはシンのいうことに聴こうとはしなかった。
そして、マコトはあろうことか教室のなかをうろうろと歩き始めた。
シンが止めに行こうとしたとき、気がついた。誰もマコトが見えていないのだ。
先生もクラスメイトも、みんな普段通りに授業を続けていた。
しかし突然見えてしまうかもしれないと思い、動き回るマコトに目をやっていたらシンは先生に叱られてしまった。
落ち着きがないと勘違いされたのだ。しかし、本当のことを言えず、ただ謝った。
これでシンは恥をかいてしまった。
「お前のせいだぞ」
シンは自分の部屋でマコトを問い詰めていた。
「ぼく、なにもしてないもん」
「お前が勝手に動き回るから、おれがしかられたんだぞ」
「ぼく、誰にも見られてないもん。悪くないもん」
「お前のせいだ。お前が悪いんだ」
「ぼくは悪くない!」
「お前がいるからいけないんだ! お前なんか消えちゃえ!」
怒りにまかせて、シンは叫んだ。するとマコトはにやりと笑った。
「消えるのは、君のほうだよ」
その瞬間、マコトが初めて出てきた日と同じような眠気を感じ、シンはその場に倒れてしまった。
太陽の光に照らされて、シンは目を覚ました。
時計を見ると、とっくに出かける時間を過ぎていた。部屋にはマコトはいなかった。
と同時に、ランドセルもなかった。
シンは不思議に思いながら、学校へと向かった。
学校に着くと学級会の始まる時間になっていた。
急いで教室に入ろうとしたが、シンの席は埋まっていた。マコトが座っていたのだ。
そしてマコトは、周りの席のみんなと楽しそうにおしゃべりをしていた。
「そ、そんな……」
教室の入り口でシンは呆然と立ち尽くしていた。気がつく者は誰もいなかった。
「ねえ、シンくんの魔法見せてよ」
「あれのこと? そんなの嘘に決まっているじゃん」
シンと呼ばれたマコトはさらりと言った。
「えーそうなの? あたし、信じちゃったよ」
「じゃあ、何を発表するの?」
「ぼくの名前のことについて。シンって父さんがつけたんだ」
「へえ」
そのとき、先生が教室に入ってきた。もちろん入り口にいるシンに気づくことはなかった。
学級会が始まり、ひとりひとりが発表を始めた。
そしてシンの番が来た。今やシンになってしまったマコトが壇上に立った。
シンはそこに駆け寄った。
「お前、何をした? なんでそこにいるんだよ」
マコトであったシンはその姿をちらりと見て、一言つぶやいた。
「はやく消えろ」
その瞬間、シンの視界はゆっくりと白くなっていった。
end