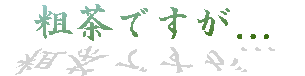日当たりの好い部屋
この部屋は日当たりがとても良かった。
ここに一人の男が暮らしていた。
彼は足が不自由だった。
週二回の配給の日にしか、外に出ることはなかった。
男には唯一、趣味と呼べるものがあった。それは絵を描くことだった。
わずかなお金で絵の具を買い、古いキャンパスの上に新しい絵を重ねていくのだ。
思い立ったときに部屋から見える景色を、黙々と描いていた。
ある日、男は珍しく早起きをした。
窓の外を眺めていると、歩道を歩く少女の姿が目に入った。
朝の風は彼女の栗色の長い髪と紺色のスカートを揺らしていた。
その時、男は強い衝撃を受けた。少女の、その美しさに。
白い肌に浮かぶのは、黒々とした瞳に小さな紅い唇。
大人に限りなく近くて、それでもまだ幼さを隠せない年頃だった。
男は少女が見えなくなるまで、その姿を見つめ続けていた。
その日から、男は朝に少女を眺めることが日課になった。
少女の姿を目にすると、日増しに男の胸に熱いものがこみ上げてきた。
そして毎日のように、少女が自分の部屋のドアを開けるのを夢で見た。
その度に喜びと悲しみを一度に味わうのだった。
燃え上がるようでいて、しかし儚く消えてしまいそうな「何か」。
心地よいようで、息苦しくもある、不思議な感覚。
それが一体、何なのかは、男にはわからなかった。
彼はそれをキャンパスに向けた。
最初に描いたのは、様々な色が混ざり合ったような絵だった。
男の心はすっきりとしたが、納得はしていなかった。
男は再び、絵を描き始めた。それは人物画――少女の絵だった。
朝に少女の姿を目に焼き付けては、筆を取る。
何度も何度も繰り返し、絵の具が重ねられていった。
絵のなかの少女は日を追うごとに現実の少女に近づいていった。
寝る間も惜しんで描いた作品は、ようやく完成した。
絵の少女は、まるで聖母のような微笑みを湛えていた。
男の身なりは汚れ、やつれていたが心はとてもしあわせだった。
これが出来上がることで、自分が少女に近づけたような気がしていた。
男にとっての光、そのものだった。
男は絵の前でひざまずいて神に感謝した。
疲れ果てた男が眠りから覚ましたのは、夜中だった。
女の悲鳴のようなものが聞こえたからだ。
窓を開けて見てみると、歩道に数人の女たちが群れを成していて、酷い罵声が飛び交われていた。
その群れに囲まれるようにして、一人の女が立っていた。
どうやら罵詈雑言を浴びているのは、その女のようだった。
そして、女は殴られた。一人、また一人と順番に。
まるで儀式のようだった。
男はその恐ろしい光景から目が離せなかった。
群れの中の女が男に目をやったので、彼は急いで窓を閉めた。
男は夢を見た。
とても懐かしい夢だった。
とても哀しい夢だった。
悪夢のような過去だった。
翌朝、男は涙を流しながら目が覚めた。
それから彼はいつも通り、少女が来るのを待っていた。
いつもの時刻に少女はやって来た。
しかし、今日はいつもと様子が違っていた。
男の部屋の前を通りがかったとき、少女は男のいる窓を見上げた。
初めて交わす視線。
突如として、男の鼓動は高鳴った。
恥ずかしさと嬉しさが同時に湧き上がった。
そんな男の心境をとは異なり、少女の表情はすぐさま曇った。
拒絶、というよりも怒りを露わにさせて。
そして次の瞬間、少女はその白く細い中指を男に向けた。
男は我が目を疑った。
それはあまりにも突然の出来事で、状況を把握する間もなかった。
困惑する男を置き去りにして少女はいなくなっていた。
男は少女が見えなくなるまで、その姿を見つめ続けていた。
太陽が突き刺すように光を放っていた。
男はそんな部屋のなかで、独り呆然としていた。
怒りとも悲しみともいえない感情が男の拳を震わせていた。
男は狂ったように叫び、部屋を荒らした。
イーゼルを倒し、絵の具を床に叩き落とし、破れている布団を更に破いた。
残ったのは、少女の絵だけだった。
すると、男はペインティングナイフを手に取った。
絵を切り裂こうとしたその時、彼は静止した。
そんな男を絵のなかの少女は慈愛に満ちた微笑みで見つめていた。
男の目には涙が止めどなく溢れてきた。
ぐちゃぐちゃになった部屋のなかで、彼は絵を抱き締めて泣き崩れた。
すでに太陽は沈んでいた。
すべてが冷たく、静かだった。
男はもう、動けなかった。
荒れ果てた部屋は時が止まっていた。
絵を切り裂くためのナイフは、彼の身を裂いたのだった。
絵の少女は男の返り血を浴びたまま、微笑していた。
end